- 社会保険の被扶養者追加の必要性と手続きの流れ
- 社会保険の被扶養者の条件と具体的な手続き
- 配偶者を扶養に入れたときの、 配偶者の国民年金についてなど
難易度と必要性
法的に必要★★★ / 条件により必要★★☆ / 法的には不要だが会社には必要★☆☆
基礎知識
労務担当者は、従業員の結婚や出産といったライフステージの変化に伴い、社会保険の扶養追加手続きに対応する機会が多くあります。扶養に追加するときは、扶養の認定範囲や、収入要件など、多くの確認事項があります。手続きを誤ると、扶養認定を取り消されてしまうこともあり、場合によっては従業員に追加の保険料負担が発生してしまうといった不利益が生じる可能性があります。正確かつスムーズに手続きを進められるよう、扶養の認定範囲や手続きの手順などをしっかりと把握する必要があります。
言葉の定義
社会保険の被扶養者とは、被保険者により主として生計を維持されている、一定の条件を満たした家族や親族のことです。
※この記事では、適用事業所で、協会けんぽに加入している企業のケースを前提に解説しています(海外に留学しているために日本に被扶養者の住所がないケースを除く)。
なぜ必要?
被保険者の扶養に入ると、保険料を自分で支払うことなく、健康保険や年金の保障を受けられるようになります。これにより、収入が少ない家族などの経済的負担が大きく軽減されます。
リスク
被扶養者になるには、さまざまな条件があります。条件を満たしているかどうかの確認を怠って届出をし、被扶養者になったとしても、後日さかのぼって扶養者から外されることがあります。この場合、扶養から外れた期間の医療費(保険給付分)を返還する必要があるほか、国民健康保険や国民年金にさかのぼって加入し、保険料を支払わなければならないなど大きな金銭的負担が生じる可能性があります。
対象企業
社会保険の適用事業所となっているすべての企業
対象者
被扶養者がいる役員・従業員
対応期間
随時
従業員・役員から扶養追加の申請を受ける
従業員の結婚・出産などで、配偶者や親族を扶養に入れたいとの申請があったら、以下の事項を確認します。項目が多いため、事前に一覧表の作成をおすすめします。なお、人事・労務管理システムなどで、必要箇所を従業員自身が入力し、申請・提出してもらう機能があるものを使用していれば、一覧を作成せずとも確認できます。
【確認すること】
・被扶養者の氏名
・被扶養者の氏名の読み方
・生年月日
・性別
・被保険者本人との続柄
・マイナンバーまたは基礎年金番号
・同居または別居
・職業
・年収(今後1年間の見込み収入額)
・被扶養者になる理由
・別居の場合、「住所」「1回当たりの仕送り額」「1年間の仕送り回数」
・被扶養者が配偶者のときは電話番号(自宅または配偶者本人)
・被扶養者になる日
・共働き夫婦の子どもなど、夫婦で共同して扶養している家族を扶養追加したいときは、共同扶養者(被保険者の配偶者)の年間の見込み収入額
・マイナ保険証の利用の可否
・資格確認書の発行要否
※海外留学などで日本に住んでいないときは、その理由(日本に住んでいない理由)も必要です。
被扶養者に該当するかを確認する
従業員が配偶者や親族を扶養に入れたいと申し出たときは、「用語」で示した「被扶養者の認定範囲」に照らして、被扶養者に該当するかを判断します。具体的には、以下の収入要件・同一世帯の条件を確認する必要があります。
【被扶養者の収入要件】
年間収入が130万円未満(60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円)かつ以下を満たす人(※)
・同居の場合:収入が被保険者の半分未満
・別居の場合:収入が被保険者からの仕送り額未満
※2025年10月1日より、扶養認定を受ける人が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)は、被扶養者認定における年間収入要件が130万円未満から150万円未満に変更されますのでご注意ください。
【同一世帯の条件】
同一世帯の条件には以下の2つがあります。
①被保険者と同居している必要がない人
・配偶者(事実婚を含む)
・子ども、孫および兄弟姉妹
・父母、祖父母などの直系尊属
②被保険者と同居している必要がある人
・上記①以外の3親等以内の親族(伯叔父母(おじ・おば)、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子ども(配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
必要書類を案内する
被保険者に対して、年金事務所へ届出するときに必要な書類を案内します。
【続柄確認のための書類】
・被扶養者の90日以内に発行された戸籍謄(抄)本または住民票
(コピー不可、マインナンバーの記載がないもの)
ただし、以下の①②のいずれにも該当する場合は、続柄確認のための書類は不要です。
①被保険者と被扶養者双方のマイナンバーを届出書に記載する場合
②戸籍謄(抄)本・住民票により被扶養者の続柄を確認し、届出書に記載する続柄と相異ないことを確認した旨を届出書に記載する場合
※事業主が確認した旨を記載していない場合でも、従業員とその配偶者の婚姻関係、または被保険者と20歳以下の子どもとの親子関係を明らかにする場合で、従業員と被扶養者に日本の戸籍があれば不要(子どもの出生をきっかけとした届出の場合を除く)。
【収入要件確認のための書類】
扶養者が収入要件を満たすかを確認するために、必要に応じて以下の①~③のケースに応じて書類を提出してもらいます。
①所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族である場合
事業主の証明があれば、収入要件確認のための書類の提出を求める必要はありません。ただし、従業員の税法上の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、収入確認の証明書類を提出してもらう必要があります(所得税法上の控除対象配偶者の適用を受けられないため)。
②上記①以外の人
以下のケースに応じて、それぞれ必要な書類を提出してもらいます。
(1)退職したことで収入要件を満たす場合
退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピー
(2)失業手当受給中の場合、または失業手当の受給終了により収入要件を満たす場合
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知のコピー
(3)年金受給中の場合
現在の年金受取額が分かる年金額の改定通知書などのコピー
(4)自営(農業等を含む)による収入、不動産収入がある場合
直近の確定申告書のコピー
(5)上記(2)~(4)以外に他の収入がある場合
・上記(2)~(4)に応じた書類
・課税(非課税)証明書
(6)上記(1)~(5)以外
・課税(非課税)証明書(※)
※障害年金など非課税対象となる収入がある場合は、受取金額のわかる通知書等のコピーが必要になります。
③別居している親族などを被扶養者とする場合
・仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類(送金者と受取人名および、仕送り額が確認できるもの)
※扶養認定を受ける人が16歳未満または16歳以上の学生の場合は不要
なお、仕送り方法によって提出してもらう書類が異なる点に留意が必要です。
(1)振込の場合
・預金通帳等のコピー(通帳の名義および振込日と金額のページ)
・振込明細書 など
(2)送金の場合
・現金書留の控え(または控えのコピー)
続柄や年収の確認書類などは、状況に応じて変わります。
事前に管轄の年金事務所へお問い合わせされることをおすすめします。
扶養家族の書類を作成し、届出する
情報が集まったら「健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」を作成し、届け出ます。
添付書類:状況に応じて必要(STEP3参照)
届出期限:扶養者になってから5日以内
届出先:事務センターまたは管轄の年金事務所
届出方法:電子申請、郵送または管轄の年金事務所へ持参(事務センターのときは郵送のみ)
手続き完了の案内をし、必要に応じて資格確認書を渡す
手続きが完了したら、その旨を従業員に伝えます。マイナ保険証を持っていれば、他に案内は不要です。マイナ保険証を持っていない場合、資格確認証書を渡します。
よくある質問
Q:配偶者を扶養に入れました。配偶者の国民年金はどうなりますか?
配偶者を扶養に入れる場合でも、国民年金に加入します。なお、第2号被保険者に扶養されている人は第3号被保険者となります。
この場合、配偶者の保険料負担は生じません。ただし、第3号被保険者とできるのは、20歳~60歳の期間にかぎります。
Q:従業員が別居している両親を扶養に入れたいと申請してきました。仕送りは現金で手渡しのときは、どういった証明が必要ですか?
手渡しのときは、証明ができません。
仕送りの証明は、客観的に確認できる書類が必要で、手渡しでは客観的な証明ができません。したがって、手渡しのときは仕送りの方法を銀行や郵便局からの振込、または現金書留に変更し、証明ができるようになってから届出されることをおすすめします。
Q:従業員に子どもが生まれました。マイナンバーがまだ届いていないときは、どういった証明が必要ですか?
90日以内に発行された戸籍謄(抄)本、住民票(従業員が世帯主で子どもと同居しているとき)のいずれかの原本が必要です。
HRbaseからのアドバイス
被扶養者の条件を満たしているかの状況確認は「被扶養者資格の再確認」と呼ばれる手続きで毎年行われます。日本年金機構から送付されるリストに基づき、企業は従業員を通じて被扶養者の収入状況などを確認し、報告する必要があります。日頃から従業員に対して、被扶養者の状況に変わりがないか定期的に確認を促しておくと、スムーズに対応できます。
被扶養者の状況を正しく確認して届出を行わないと、状況確認のときなどにさかのぼって被扶養者から外されることがあります。さかのぼって被扶養者から除外されると、健康保険証や年金の手続き、支払いが発生します。この場合、保険料負担が高額になることも考えられます。こうしたことを回避できるよう、企業は被扶養者の条件を確認し、不明点があれば、管轄の年金事務所へ事前に問い合わせることをおすすめします。
関連記事

社会保険労務士。株式会社HRbase代表取締役/社会保険労務士法人HRbase代表。労務管理の課題をITで解決できる社会を目指す。HRbase Solutionsは三田をはじめとする社会保険労務士、人事労務の専門家、現場経験の豊富なプロと、記事編集者がチームを組み「正しい情報×徹底したわかりやすさ」にこだわって作り上げているQAサイトです。



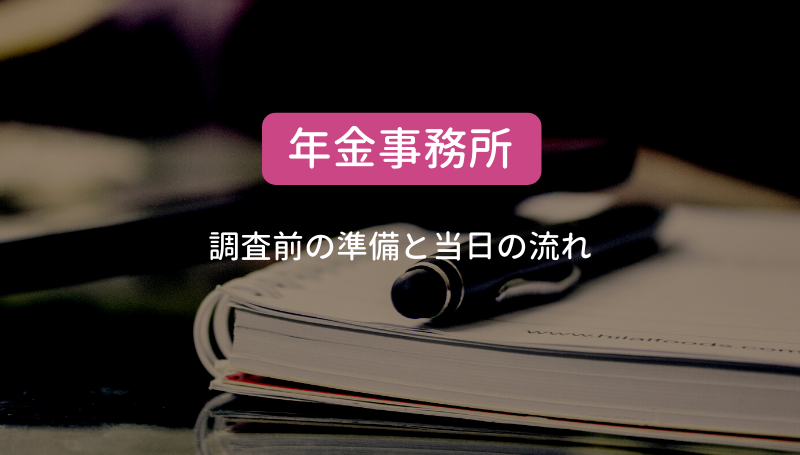
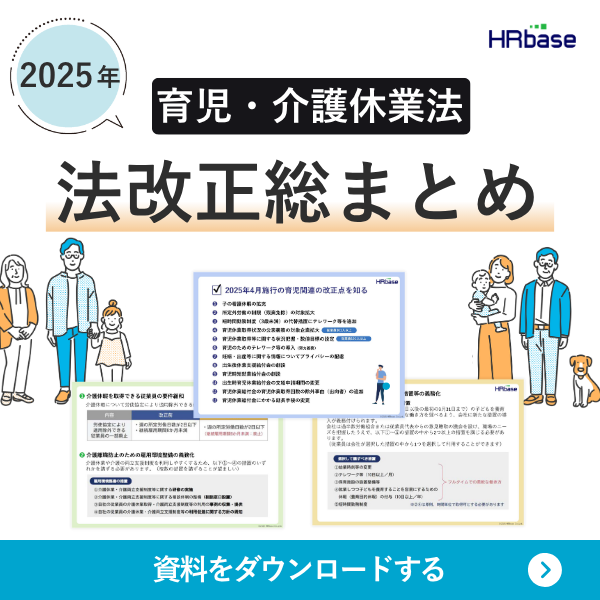
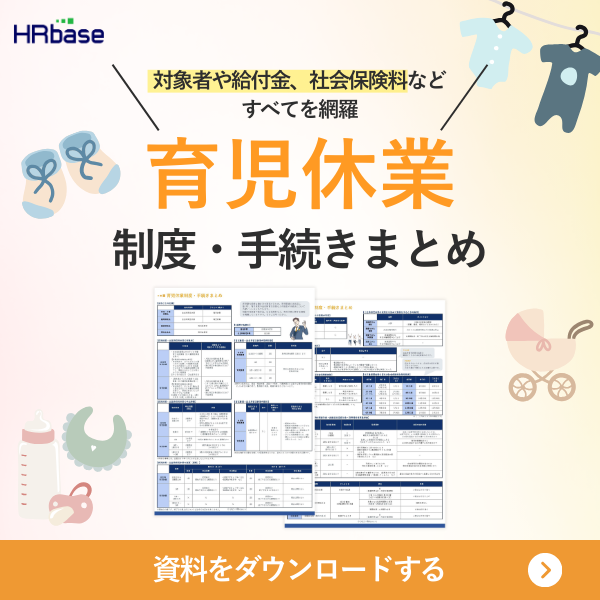
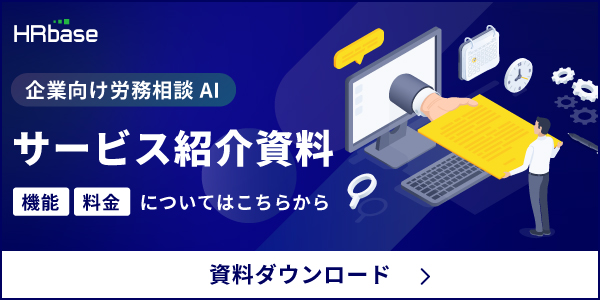
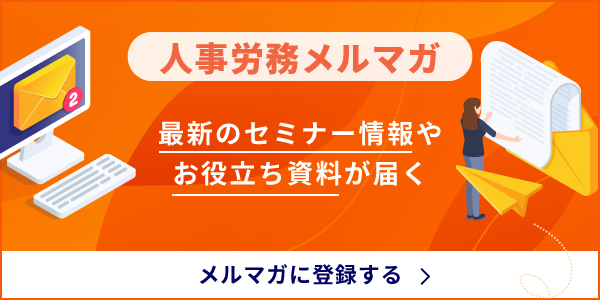
 で
で