- 育児短時間勤務制度の必要性と対象者
- 育児短時間勤務の申請フロー
- 男性も育児短時間勤務制度を取得できますか?など
難易度と必要性
法的に必要★★★ / 条件により必要★★☆ / 法的には不要だが会社には必要★☆☆
基礎知識
育児短時間勤務制度は、子育て中の従業員が利用できる、法令で定められた権利です。制度への理解を深め、男女を問わず気兼ねなく利用できる社内風土を作ることが重要です。
言葉の定義
【育児短時間勤務制度】
3歳未満の子どもを養育する従業員が、希望すれば1日の所定労働時間を原則6時間に短縮できる制度です。この制度は「育児・介護休業法」により、企業に導入が義務付けられています。
なぜ必要?
育児短時間勤務制度は、仕事と子育ての両立支援を目的につくられたものです。制度の活用は、子育て中の従業員が育児の負担や時間的制約によって離職せざるを得ない状況を防ぐために有効です。
従業員が安心して働き続けられるよう、企業は多様な働き方を推進する必要があります。
リスク
育児短時間勤務制度は、適切に運用しない場合、法令違反となるリスクがあります。
また、従業員が復職後直後から育児短時間勤務制度を取得する場合、社会保険の手続きが必要なケースが多いです。手続きを忘れると、従業員が将来受け取る年金額が本来より少なくなってしまう可能性があるため、注意が必要です。
対象企業
従業員を雇用するすべての企業
企業と従業員代表で結ぶ労使協定書で、一定条件の従業員は除外できます。
【労使協定により対象外にできる従業員】
・入社後1年に満たない従業員
・1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
・業務の性質から短時間勤務を行うことが困難な従業員(※)
※「業務の性質から短時間勤務を行うことが困難な従業員」を労使協定により対象外とする場合は、該当する従業員に対して以下の代替措置を講じる必要があります。
・フレックスタイム制
・時差出勤制度
・従業員の3歳に満たない子どもにかかる保育施設の設置運営、その他これに準ずる便宜の供与
・テレワーク等(2025年4月から追加)
対象者
3歳未満の子どもを養育する、以下のすべてに該当する従業員が対象になります。
・1日の所定労働時間が6時間以下でない
・日々雇用される従業員でない
・短時間勤務制度が適用される期間に育児休業を取得していない
・労使協定により、制度の対象外とされていない
実施期間
随時
メリット
制度を活用することで、以下のようなメリットがあります。
・保育所の送迎や医療機関を受診しやすくなる
・育児休業からのスムーズな復職が可能になり、育児を理由とした離職防止につながる
これらは、企業が従業員のワークライフバランスを守ることにつながります。
デメリット
短時間勤務制度の利用期間が長くなることで、以下のようなデメリットが生じる可能性があります。
・従業員自身がキャリアに対する不安を抱える
・業務の偏りや引継ぎの不備により、他の従業員の負担が増加する
こうしたデメリットを防止するために、短時間勤務を実施する従業員本人だけでなく、上司や同僚などを含めたフォロー体制を整えることをおすすめします。
やること
従業員から、育児短時間勤務の申請を受ける
育児短時間勤務の開始日の前までに「育児短時間勤務申出書(任意書式)」を提出してもらいます。提出締切日は企業で決められますが、育児短時間勤務開始日の1か月前までを期日とするのが一般的です。
申出書を受け取ったら、従業員が希望する短時間勤務の取得期間や勤務時間が、就業規則等で定めた期間と相違ないかを確認します。
育児短時間勤務の期間等を通知する
「育児短時間勤務取扱通知書(任意書式)」で決定した短時間勤務の期間や勤務時間などを通知します。通知書を渡すときは、短時間勤務の取得で給与や社会保険料などがどう変わるのかもあわせて説明します。
育児短時間勤務を取得する従業員と、その取得期間を社内に周知する
育児短時間勤務を取得することで、業務に支障がでないよう調整します。また、他の従業員の理解を得るため、育児短時間勤務制度についても周知を行います。育児休業を取得していた従業員が復職直後から短時間勤務を開始するときは、復職日も一緒に周知します。
育児短時間勤務を開始する
育児短時間勤務開始後は、残業等で終業時刻が通常の勤務時間と変わらないなど、誤った運用になっていないか、定期的な確認をおすすめします。このときに、正しく運用ができていない事実を把握した場合、業務内容の見直しを行います。
社会保険の手続きをする
育児休業を終え、復職と同時に短時間勤務制度を取得し給与が下ったときは、以下の①②の書類を作成し、事務センターに提出します。
①育児休業等終了時報酬月額変更届
②養育期間標準報酬月額特例申出書
ただし従業員が希望しないときは、手続きをしなくてもかまいません。
申請先:事務センターまたは管轄の年金事務所
提出方法:電子申請、郵送、窓口持参(年金事務所のみ)
育児短時間勤務が終了する
子どもが3歳に達する日(誕生日の前日)、または従業員が希望した育児短時間勤務の取得期間の終了日の翌日から、通常の勤務時間に戻します。
育児短時間勤務の終了日までに面談を行い、通常勤務に戻ったときの労働条件や業務内容について説明をしておくとよいでしょう。
よくある質問
Q:男性従業員でも育児短時間勤務を取得できますか?
育児・介護休業法では、男女問わず、3歳未満の子どもを育てる従業員が希望した場合、育児短時間勤務を取得させなければならないと定められています。男性従業員から育児短時間勤務の申請があったときは、取得を拒んではなりません。
Q:育児短時間勤務の申請は、いつまでにしなければなりませんか?
育児短時間勤務の取得の申請を「いつまでにしなければならない」という法令等の定めはなく、企業で自由に決められます。したがって、従業員が企業に対し短時間勤務の取得申請をいつまでに行うのかは就業規則などに記載し、従業員に周知しておかなければなりません。多くの企業では、引き継ぎや業務の見直し期間を考え、短時間勤務取得の申請期日を1か月前としています。
Q:短時間勤務を取得予定の従業員がいます。勤務時間が週30時間未満になると、社会保険は喪失になりますか?
元の労働契約が変わるわけではなく、国の制度を利用して一時的に勤務時間が短縮されるだけなので、社会保険の資格は喪失しません。
そのため、従来の労働契約の内容を変えずに育児短時間勤務制度を利用するとき、社会保険の手続きは基本的に発生しません。しかし育児短時間勤務を利用する前の労働契約の内容を変更(固定残業代がなくなる、出勤日数が減って交通費がなくなるなど)するときは、社会保険の変更の手続きが必要になる可能性があります。
Q:育児休業を取得せずに、育児短時間勤務を取得する従業員がいます。短時間勤務を取得した分は給与が下がるので、随時改定の対象になりますか?
社会保険料は以下のケースに該当したときに変更されます。
・従業員が育児休業から復職後すぐに育児短時間勤務を取得したとき
・雇用契約書に記載している固定的賃金(基本給、手当など)を変更したとき
育児短時間勤務は労働契約の変更ではないため、随時改定の手続きはできません。
Q:賞与を年2回支給しています。育児短時間勤務を取得する従業員に、賞与を支給しないようにできますか?
育児短時間勤務の取得を理由とする、解雇や降給、賞与の減給などは禁止されているため、そのような取扱いはできません。ただし、労働時間は短縮するため、短縮した時間分の減額などは差し支えありません。
関連記事
HRbaseからのアドバイス
育児短時間勤務を取得した従業員に対して、昇給させない、賞与を支給しない、あるいは降給させるなどのケースが時折見受けられます。育児短時間勤務制度は、育児・介護休業法で定められている従業員の権利です。法令を守って取得している従業員に対して不利益な取り扱いをすることはできません。確かに、育児に関する制度はややこしく、手続きも煩雑です。制度を正しく理解し、法令違反にならないような運用を心掛ける必要があります。

社会保険労務士。株式会社HRbase代表取締役/社会保険労務士法人HRbase代表。労務管理の課題をITで解決できる社会を目指す。HRbase Solutionsは三田をはじめとする社会保険労務士、人事労務の専門家、現場経験の豊富なプロと、記事編集者がチームを組み「正しい情報×徹底したわかりやすさ」にこだわって作り上げているQAサイトです。





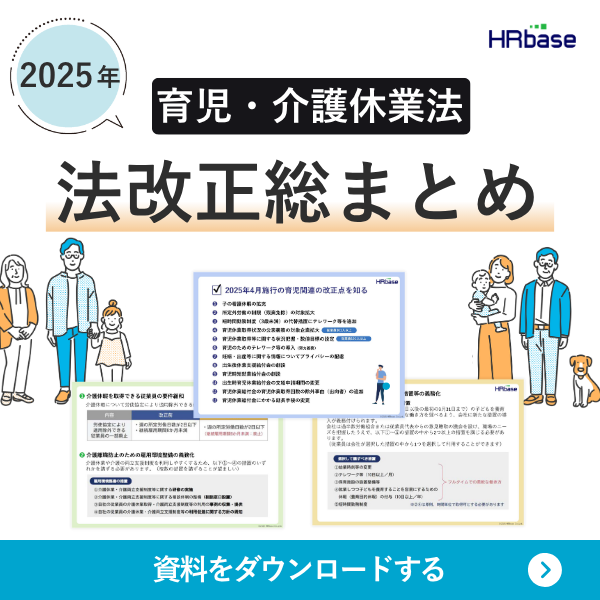
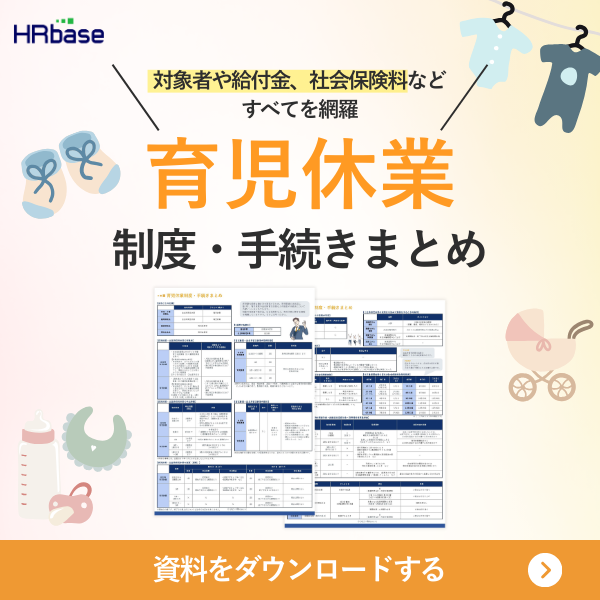
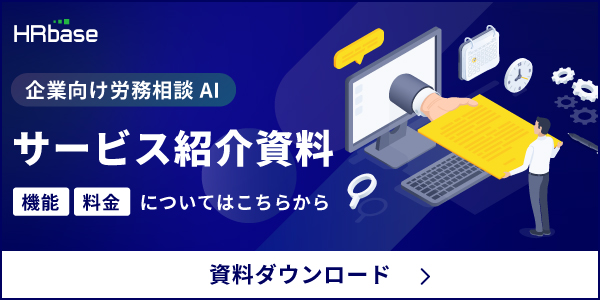
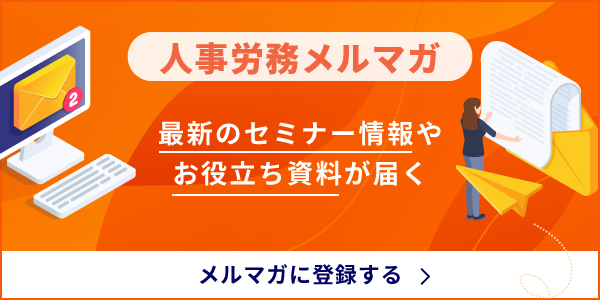
 で
で